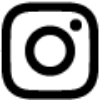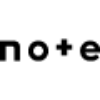【京丹後の食をつくるひと】vol.2 作り手と食べ手をつなげる「メディア」になりたい。tangobar(タンゴバル)の ”ごちそう缶詰” が生まれるまで

海と山に囲まれた自然豊かな京丹後には、食の恵みがたくさん。冬には牡蠣が豊富に獲れ、ジビエやジャージー牛も有名です。一方で、生産現場では食品ロスなど流通における課題もあります。おいしいものをおいしい状態で、できるだけ無駄なく届けたい。今回はそんな想いを「缶詰」を通じて形にする「tangobar(タンゴバル)」の関奈央弥(せき なおや)さんを取材しました。
tangobar(タンゴバル)
京丹後で缶詰を主とした食品開発や、ローカルフードツアーなど、食にまつわるサービスを展開する。
地元・京丹後の食を広めたい。小学校の栄養士から一念発起

京丹後を中心に、食の生産に関わる事業者の方と連携して、小ロットからの食品缶詰事業を行っている「tangobar(タンゴバル)」。生産者と消費者の距離を近づけるというコンセプトで、食品を長期保存できる「缶詰」にして届けています。
主宰する関さんは、京丹後市出身。tangobar(タンゴバル)という屋号は、当時東京で働いていた関さんが、地元京丹後のおいしいものを広めたいという思いから、休日にシェアスペースを間借りして開いていたバルの名前が由来です。
元々は東京の小学校で、栄養士として働いていたという関さん。地元京丹後に戻り、缶詰加工業を始めるまでにはどんな経緯があったのでしょうか。
東京のどまんなかで「地産地消」を伝えて気づいたこと
学生時代はサッカーに打ち込んでいた関さん。その中でアスリートの体作りを支える「食」に興味を持ち、大学では栄養学を専攻。食の大切さを伝える仕事がしたいと、学校給食の栄養士になりました。
関さん:
「当時ご縁のあったのが東京の大田区にある小学校で、5年ほど栄養士として、食育に取り組んでいました。私自身が地元(京丹後)の食材のおいしさを感じながら育ってきて、そこに誇りを持っていたので、子どもたちにも、地産地消や地域に伝わる行事食のことなど、この地ならではの食の豊かさを伝えることを大事にしたいと思ったんです」
東京と聞くと都会のイメージはありますが、探せば付近にはおいしい野菜を育てる農家さんがいます。そこから仕入れる野菜を使うことで、地産地消の話を子どもたちに伝えていました。その中で、江戸川にある小松菜農家さんと知り合ったことが、今の活動のきっかけになりました。
食材の背景にある「物語」を伝えると、人の心は動くと気づいて
関さん:
「小松菜は栄養価も高くて、彩りもよく、使い勝手のいい野菜。はじめは仲介業者を通じて農家さんから仕入れていました。そうやって東京の野菜を使い、子どもたちに地産地消の話をしていると、『地産地消』という言葉の意味は皆理解してくれるようになったんですね。
けれど、それ以上に繋がるかといえば難しい。子どもたちが大人になって、実際に地産地消をしようと思うほどに印象的な体験が与えられているかと考えたら、足りない部分があるなと感じました」
それならまず、自分自身が体験してみよう。当時は業者さん経由で野菜を仕入れていて、関さん自身、野菜を作る農家さんと直接コミュニケーションをとることはありませんでしたが、週末を利用して、野菜が作られる場を直接訪ねるようになったといいます。
関さん:
「実際に畑へ行くのと行かないのでは、私自身の受け取り方も違いました。畑で収穫をお手伝いさせてもらって、野菜ができていく様子を写真に撮り、作り手の話を聞く。それを学校に持ち帰り、子どもたちに話すと、子どもの心が動いていく様子を実感したんです。
それまで小松菜嫌いだった子が食べるようになり、小松菜農家さんをゲストティーチャーとして迎え課外授業を行ったときは、子どもたちが農家さんに話を聞きたいと集まってサインをせがむほど。スターのようでした(笑)」
人からの受け売りではなく、自分が直接産地を訪ねて聞いたこと、見たことを、自分の言葉で伝える。効率的ではなくても、結果としてそれが人の心を動かすことを感じた関さん。
そんな経験を経て、目を向けたのは地元京丹後の食材。食の生産者が沢山いるこの町を、自分なりに見つめ直し、知り直すことで、誰かに魅力をシェアできるのではないか。それからは週末のたびに夜行バスで地元へ帰り、気になる生産者を訪ね、その食材を東京で人々に振る舞う「tangobar」の活動をスタートさせました。
活動を進めていくうちに、京丹後出身の料理家や生産者と広く知り合うようになり、
学校という幅を超えてやりたいことが広まっていくのを感じるように。
そしてついに、Uターンを決意。地元で生産者の物語と食材を届けるメディアのような存在になりたいと思い動き始めたのです。
つくる人と食べる人を伝える手段が、京丹後で出合った「缶詰」
そこから缶詰事業を始めるまでの経緯は、本当に偶然。新規事業を始める上でさまざまな人に出会い話を聞くうちに、缶詰の製造を行う地元の方と知り合い、そこで仕事のお手伝いをするうちに、缶詰のもつ可能性に気づいたといいます。
関さん:
「京丹後には、山にも海にもおいしい食材が豊富にあります。けれど実際に生産現場を訪ねると、それを流通させる仕組みが整っていないことに気づきました。
たとえば、牡蠣。京丹後は冬に牡蠣が豊富にとれることで有名ですが、私たち消費者が『食べたい』と思うのは冬の間だけ。桜開花のニュースがで始めると牡蠣の存在は忘れられ、実際の収穫は4月まで続くのに、市場に出してもあまり値段がつかないそうなんです。
そこにとれたての牡蠣を長期保存できる缶詰という仕組みがあれば、市場に出す以外の活用法ができます。生産者さんにとって、大切に育てた食材の販路の選択肢がひとつ増やせることには意味があると感じました」
そこから、缶詰の製造事業に本腰を入れ始めた関さん。ちょうど地域の食材を加工する施設「リフレ農産加工施設」が缶詰事業を始めた時期で、協力して加工、製造する仕組みを作り上げていきます。
こうして、大手のように大ロットではなく、百数十単位からの製造が可能な、小規模事業者向けの缶詰製造が実現していったのです。
パッケージに綴る物語。缶詰は「読んで食べられるメディア」
そこからの関さんの行動力はすごいもので、缶詰の製造ノウハウを学びながら、時間を見つけては京丹後の生産者さんを訪ねて回る日々が始まりました。
今のtangobarの代表商品のひとつである「アヒージョ缶」シリーズに使われている魚介類も、地元では有名な漁師さんの生産現場を訪ねて仕入れているものです
関さん:
「牡蠣の缶詰は、旨味が強くておいしいと有名な久美浜湾の牡蠣を使っています。久美浜湾にはいま100件ほどの漁業者がいますが、生産者の高齢化などさまざまな問題がある中で、牡蠣の養殖を未来にも継いでいきたいと若手の方も頑張っているんです。
タコの缶詰は、宮津で『スーパー漁師』と呼ばれている本藤さんという方が獲るタコを使っています。それから、同じく宮津でイワシ漁を行う村上さんのイワシも。まだ20代なのですが、強い思いを持って漁業に取り組んでいるんですよ」
実際に現場を訪ねたからこそ、伝えたい想いがたくさんある関さん。そんな物語は、缶詰のパッケージに記し、味とともに届けられています。
関さん:
「いただく食材がストーリーの詰まったものばかりなので、ただ味を伝えるだけでは勿体無い、しっかり背景も伝えたいと思うようになりました。言わば缶詰は ”食べられるメディア”
なのかもしれません」
保存食という概念を超えた「ごちそう缶詰」をめざして

そんな思いが詰まった缶詰は、もちろん味もお墨付きです。
湯煎で熱々に温めた「久美浜湾の牡蠣のアヒージョ」を開けてみると、缶にみっちりと詰まった大ぶりの牡蠣。濃厚で身がしっかりとした牡蠣は、にんにくとオリーブオイルの香りが食欲をそそり、オイルまで余すことなくパンにつけて食べたい味。缶詰というよりは、まさに一品料理のようです。
関さん:
「ちょうど今朝も漁を見に行ってきたのですが、朝採れた牡蠣をその日のうちに缶詰に加工しているんです。ここまで鮮度に関わって作られる缶詰はそうそうありません。
缶詰といえば保存食のイメージが強いと思うのですが、これは本当に美味しい。僕はこれを『ごちそう缶詰』という新たなジャンルの料理だと思っています」
既存の缶詰の概念を超えて、より多くの人に、幅広い機会に食べてもらえるように。「ごちそう缶詰」の提案をこれからも模索していきたいと関さんは話します。
京丹後に、当たり前のようにある「豊かさ」を残していくために
関さん:
「京丹後は車で1時間もあれば移動できる距離の中で、自然環境を活かし、多様な食材が生産されています。野菜、肉、魚牛乳・乳製品や醤油といった調味料まで。こんなに多くの食材が揃う地域は、国内でも多くありません。
僕はそれが当たり前のこととして育ってきましたが、今はその豊かさを実感しています。だからこそ、その文化がなくならないように守っていきたい。作り手の魅力と、味の魅力を、缶詰を通して人に伝えていくことが、僕にできる ”食育” の形なのかなと考えています」
まだまだやりたいことが沢山ありそうな関さん。tangobarはここ京丹後で、これからどう活動を広げていくのでしょうか。小さな缶詰に、京丹後の食文化を支える、大きな可能性を感じました。
Writer:瀬谷 薫子
Writer & Editor|doyoubi店主
https://note.com/doyoubi_muffin/